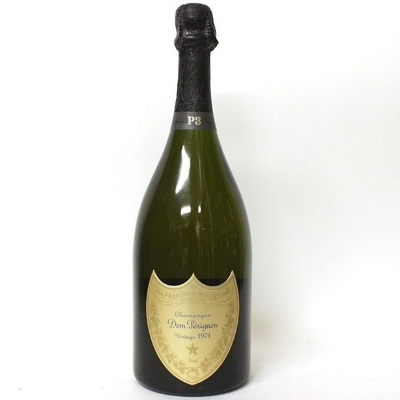ウイスキー買取で高く売る!相場・人気銘柄・高額査定のポイント
近年、ジャパニーズウイスキーやスコッチの人気が高まり、世界的に需要が拡大しています。特にサントリーの「山崎」「響」洋酒では「マッカラン」といった銘柄は品薄状態が続いており、中古市場でも高値で取引されています。そのため、ご自宅に眠っているウイスキーが思わぬ高額査定につながる可能性があります。
買取で人気のウイスキー銘柄
ウイスキー買取の相場目安
高く売れる条件
高く売るためのポイント
まとめ
買取で人気のウイスキー銘柄
高額買取されやすい銘柄には以下があります。
マッカラン(シェリーオーク、旧ボトル、限定品)
山崎(18年、25年、リミテッドエディション)
白州(18年、NVも人気上昇中)
響(21年、30年、意匠ボトル)
ボウモア・アードベッグなどアイラモルト(限定リリース)
軽井沢・竹鶴など終売ボトル
ウイスキー買取の相場目安
山崎 18年 … 7万円〜12万円
響 21年 … 6万円〜10万円
マッカラン 18年 シェリーオーク … 5万円〜8万円
響(21年、30年、意匠ボトル)
軽井沢 旧ボトル … 数十万円以上
※保存状態・付属品の有無・流通時期によって変動します。
高く売れる条件
ウイスキーは保存状態や付属品が大きく査定に影響します。
未開封で液面が高い(蒸発や劣化がないことが重要)
箱・替栓・冊子が揃っている
ラベルに汚れや剥がれがない
限定ボトル・終売品 は特に高額査定対象
高く売るためのポイント
複数本まとめて査定 → まとめ売りで査定額UP
買取強化中の銘柄をチェック → 店舗がキャンペーンを実施している場合が多い
相場が上がるタイミングを狙う → 年末年始・ボーナス時期は需要増
専門店に依頼する → 一般リサイクルショップより高額査定
まとめ
ウイスキーは、ただの古酒ではなく「資産」としての価値を持っています。特に人気銘柄や旧ボトルは、数万円から数十万円で取引されるケースも珍しくありません。
✨ 当店では「山崎」「響」「マッカラン」をはじめ、希少ウイスキーを 高価買取強化中!
査定は無料、1本からでもOK。お気軽にご相談ください。